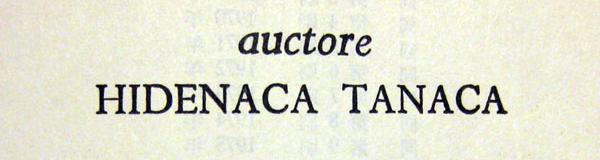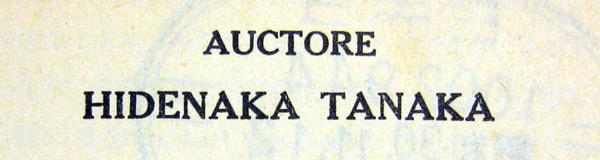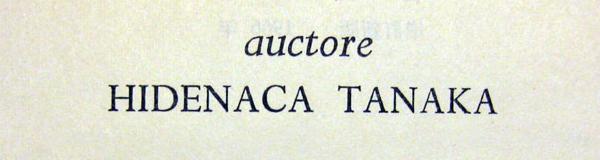田中秀央の著作を見て感じる疑問ふたつ。
外国語の文法書の最初の章には大抵、文字とその発音の解説がある。
ラテン語の文法書でも同じで古典期ラテンには W は無いとか、I と J、U と V の区別とかの説明があって、K については大抵
「K は Kalendae(朔日)以外に用いられる事は極めて稀」等とあり、発音については「C は常に [k] 音」と説明されている。
ca, ci, cu, ce, co でカキクケコ。 ローマの将軍シーザー Caesar はカエサルと読む方が本来の音に近い。
だから菌類の学名の属名語尾によく付いている -myces はミケスと発音するのだ、とよく説明されているし私も何度か聞かされた。
でもそんな古典期ラテンにより近い読み方 (Reformed academic) よりも英語風の読み方 (Traditional English) の方を聞く事も多い。
たとえばアオカビ Penicillium はペニキリウムではなくペニシリウムとなっている事が多いようだし
酵母菌 Saccharomyces cerevisiae のサッカロミケス・セレヴィシエというのも慣用読みだろう。
私自身は学名を声に出して読むことはほとんど無いので、頭の中で適当にローマ字読みをしている。
ラテン語である学名にはアルファベット使用上の制約は無くて(ラテン語として発音の難しい語は避けるべきという勧告はあるが)
W や K も普通に使われていて普段は気にならないがたまにラテンの詩文を眺めると確かに K が無いなあ、などと思う程度だ。
普段、ラテン語辞書は研究社の羅和辞典(増訂新版)を使っている。
もうすぐ全面的に改訂された新版が出るようだが、初版から数えると半世紀に亘って刷りを重ねてきた辞典である。
著者の田中秀央(京都大学名誉教授、1886-1974)は日本の西洋古典学研究の先駆者的存在である。
出身が同じ愛媛県である事、(後で知ったことだが)晩年の住まいが私の学生時代の下宿のすぐ近くだった事、
三高の学生時代、田中は土曜日になると京都の東山、鹿ヶ谷から大文字山に登って銀閣寺に降りてくるのが常だったらしいが、
それが私のキノコフィールドの一つだったりで勝手に親近感を感じている。
明治末期のこのあたりで田中もいろいろなキノコを見たに違いないが今とは随分違ったのだろうか等と想像する。
それはさておき、この羅和辞典の標題紙にある著者田中秀央のラテン語表示「Hidenaca Tanaca」を見るたびに
これは「ラテンでは [k] 音は C」という田中のラテン語学者としてのこだわりなのだ、とずっと思っていて
今でも決して「食える学問」ではないギリシャ・ラテン語を一世紀も前に志した彼の学問に対する真摯さみたいなものを感じていた。
(下図は 1985 年出版の増訂新版 19 刷の標題紙、著者のラテン語表記部分)
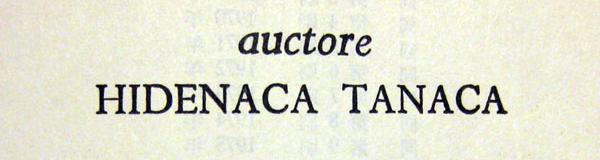
だが、実際はどうだったのだろうと最近では思っている。
それは羅和辞典の初版では普通に Hidenaka Tanaka となっているのを知ったからだ。(下図は 1953 年出版の初版 3 刷)
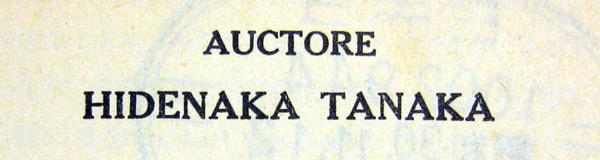
田中の他の著作ではどう表記されているのだろう。いくつか調べてみた。例えば...
「羅甸文法」では Grammatica Latina / auctore Hidenaka Tanaka.
「新羅甸文法」では Nova grammatica Latina / auctore Hidenaka Tanaka.
「希臘語文典」では Graecae grammaticae rudimenta in usum scholarum / auctore Hidenaka Tanaka.
「マーグナ・カルタ」では Magna Carta cum translatione japonica / auctore Hidenaka Tanaka.
田中が大正14年に提出した博士論文の自筆標題は「De quin particula latina eisque usu historico ... / scripsit Hidenaka Tanaka」である。
どれもラテン語表記中で K を使っていて C を使っている例は改訂版羅和辞典以外には見当たらないようだ。
田中の旧蔵書には蔵書票 (Ex Libris) が貼られているが、その文面は「Festina lente / Ex libris / Hidenaka Tanaka」とあって
(Festina lente はラテン語で「ゆっくり急げ」の意味。恩師ケーベルの教えで、田中はこれを生涯の座右の銘とした。)
ここでも K が使われている。自筆サインもすべて Tanaka である。(もっともこれは普通のローマ字表記だろう。)
羅和辞典の標題紙の表記が Tanaka から Tanaca に変更されたのは博士の意向だったのだろうか。
そんな事を思いながらふと増訂版の初刷を見ると Hidenaca Tanaka となっていた。
この中途半端さはいったいどうした事だろう。(下図は 1966 年出版の増補改訂)
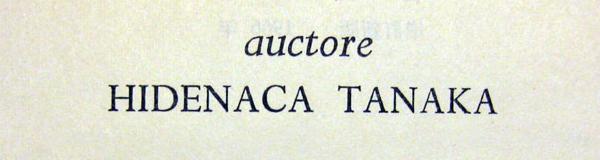
改訂版の初刷の版表示は「増訂新版」ではなく「増補改訂」となっている。
初刷と第2刷以降はわずかな誤植の訂正以外はなされていないようだが、
Tanaka から Tanaca になったのが「増補改訂」から「増訂新版」という表示に変えられた所以だろうか。出版社に聞いてみた。
既に当時の詳細な記録は残っておらず K から C へ変えられた確かな理由はわからないがおそらく博士の意向だろうとの返事を頂いた。
著者に無断で出版社側で変更するような事はしないはずだから何か表記に関して提案が有ったと考えるのが自然だが
そうだとしたらわざわざ C に変えた田中の真意は何だったのだろう。
(標題紙の著者表示の Tanaka が Tanaca に修正されて姓名の表示が揃ったのは改訂版4刷かららしい。
一方で背表紙の表示は新旧版を通じてずっと Tanaka のままである。)
***
田中の著作を見てもう一つ疑問に思う事はその出版年表示についてである。
和書では出版年は奥付に表示するのが普通だが洋書では大抵標題紙に出版年を表示する。
田中の著作の中でラテン語タイトルがあるものはこの慣例に従って標題紙に出版年が記されているものがいくつかある。
初期の著作である「羅甸文法」では普通に 1916 と西暦年で表示されているのに
1929 年出版の「新羅甸文法」には MMDLXXXIX (2589)、1932 年出版の「希臘語文典」では MMDXCII (2592) とローマ数字で表示されている。
これは皇暦だ。神武天皇の即位年から数える皇暦は西暦に 660 を加えた数字になるが、戦前は比較的普通に使われていた暦法である。
紀元2600年(西暦1940年)の昭和15年には各地で祝賀行事が行われた。
明治時代の歴史の教科書を見ると年号が皇暦で書かれていて戸惑う事があるし
年号を覚える語呂合わせ「鳴くよ (794) ウグイス平安京」も「平安京は一夜越し (1454)」などと覚えたそうである。
だが出版年表示で皇暦を見かけることは戦前の和書でもかなり珍しく、まして日本で出版された洋書で皇暦を使っている例は非常に少ない。
田中は博士論文にも提出年を自筆で MMDLXXXV (2585) と記してあるし、その他幾つかの著書の序文にも皇暦で日付を記している。
どうやら 1916 年以降に皇暦を使うようになったようだ。そしてこの変化は田中の残したサインに一層明瞭に現れる。
田中の旧蔵書は京都大学の退官に際して西洋古典学関係の洋書を中心に 2000冊程が大学に寄贈され
現在も京都大学文学部図書館に田中秀央文庫として収められているのだが、ほとんどの本に日付入りのサインが書き付けられている。
大抵は見返しかタイトルページの右上に、名前、年月日、場所の順で「H. Tanaka. 27.iv.1916. Tokyo」という風にペン書きされている。
判読できないものも僅かにあるが、調べた限りでは「1909.xii.30」と日付のあるサインが一番古い。
イギリス留学中(1922-1924 年)の Oxford とあるサインも多く20代前半から寄贈直前までの40年近くに亘っているのだが
そのサインを年代順に並べてみると面白い事がわかる。筆致や月日の書き順も年代に従って微妙に変化があるけれど
1916 年を境に年の書き方が変わるのだ。1916 年までは全て西暦で書かれているが、1917 年以降は全て皇暦表記になる。
(ただし和書への書き込みは日本語縦書きで、その日付は元号表記である。)
境目となる 1916 年と表記のあるものを詳しく見てみると 4月 27日付けのものがかなりある。
そのほとんどに「J.L. Libr.」と田中の書き込みがあるが、これは東京帝国大学の英語教師ジョン・ロレンス(John Lawrence)の遺品である。
ロレンスは同年 3月 12日に亡くなったが、その遺品を友人の市河三喜と共に整理した際に譲り受けたものだ。
そのほか、2月 16日、6月 3日、9月 18日、10月19日等の西暦表記のサインが残っている。
一方、5月 5日付けで最初の皇暦表記 (2576) のサインが一つだけある。そして翌年「2577.i.15」のサイン以後は全て皇暦で書かれている。
「田中秀央 近代西洋学の黎明」(京都大学学術出版会, 2005) の口絵には田中が書いた座右の銘「Festina lente」の文字が掲載されているが
その右下には「MMDCXXVI [2626, 西暦=1966] H.Tanaka」 のサインが読み取れる(ここでも K を使っている)ので、戦後も使っていた事がわかる。
1917年に突然皇暦を使い始めたのはなぜだろう。
田中は 1914年の夏に結婚し翌年に長女、1917年に次女が誕生と幸福な時期である一方、夫人を肺結核で 1918年に亡くしているのだが
特にこの時期に皇暦にこだわるようになる事があったのだろうか。
皇暦でサインを書き始めた 1917(皇暦 2577)年のサインには西暦で 19 と書きかけた後でそれを消して 2577 と書き直しているものもあり、
日付を皇暦表記する事に慣れていない反面、書き直してまでも皇暦で書こうとしているのがわかる。
さらに 2590年には 2月 30日という日付のサインがある。
この一見奇異な日付を見ると、月日の書き方にも一つの疑問が沸く。田中は旧暦を使用していたのではないか。
旧暦は 2月も 30日まであるし(年によって 29日までの事もあるが皇暦 2590=西暦 1930 年は 30日まで)逆に 31日までの月は無い。
そして偶然かもしれないが田中のサインにも 31日付けのものは見当たらない。
もしそうなら年は皇暦で、月日は旧暦でという普通では考えられない方式でサインしていた事になるのだが。
さらに不思議な事にその皇暦が間違っているものがある。
例えば 1923年出版の本に出版年以前の日付である 2561(西暦=1901)と書いてあったりするし
Oxford での日付で 2853(明らかに 2583=西暦 1923 年の誤記)とあったりする。また 2560 と書かれている本が何冊かある。
正しい日付なら西暦 1900年だが田中はまだ 14才だし、どの本もこれ以降に出版されたものなので間違いなのは明らかである。
それが一つだけならまだしも、5月 9日、7月 15日、8月 25日等複数日に亘っていて、この時期はずっと勘違いしていたのではないかと思われる。
伝記によれば田中は毎朝 6時に起床、回数を決めて深呼吸や冷水摩擦をし、大学の研究室まで 2650歩等と数えていたというのだが
それほどまでに数字に几帳面な田中が皇暦を使い慣れていたのなら間違う事はありえない。
蔵書へのサインと自著の出版年表示には何らかの理由であえて皇暦を使っていたように思うのだ。
(2009.03.11 記)